「コンセントが足りないから延長コードで…」
「とりあえず安いやつを使っている」──そんな人は要注意!
延長コードや電源タップは、ただの配線道具ではありません。選び方を間違えると、ブレーカーが落ちる・火災の原因になる・スマホの充電が遅いなど、さまざまなトラブルの元になります。
特に在宅ワークやテレワークの普及により、自宅で複数の電子機器を同時に使うケースが増加。
今や“電源まわり”は、快適な作業環境づくりに欠かせない要素となっています。
この記事では、
- 延長コード選びで失敗しないためのポイント
- 使用目的別・安全&便利なおすすめ10選
- 配線のトラブルを防ぐ使い方・注意点
をわかりやすく解説。
見た目も機能も妥協しない、そんな“賢い選び方”を知りたい方は必見です!
延長コード・電源タップを選ぶ前に知っておきたいこと

コンセント周りのトラブル事例
私が身近で聞いたトラブルの一つが、同じ電源タップにPC・モニター・加湿器・ヒーターをつないでいた結果、ブレーカーが落ちてしまったというもの。
このように電流が一箇所に集中すると、家全体の電源が落ちてしまう事例は珍しくありません。中には「ブレーカーが落ちても、戻せばいいだけ」と軽く考える方もいますが、同じ状況を繰り返すのは非常に危険です。
たこ足配線による発熱や、コンセントまわりに溜まったホコリが原因となる“トラッキング火災”のリスクも見過ごせません。
延長コードは便利な反面、正しい知識と使い方が求められるアイテムです。
延長コードは「ただの配線ツール」ではない
延長コードや電源タップは、単なるコンセントの延長手段と考えがちですが、最近の製品はUSB充電ポート付きや雷サージガード付き、個別スイッチ搭載など高機能化が進んでいます。
正しく選ぶことで、安全性・利便性が向上し、配線ストレスのないデスク環境を整えることができます。

多くのガジェットや機器類に囲まれる在宅ワークでは、延長コード・電源タップは切っても切れない存在。
便利なアイテムだからこそ、正しく選び、正しく使うということを常に意識しましょう!
【注意】古い延長コードをそのまま使い続けていませんか?
延長コードは消耗品です。経年劣化で被膜が硬化したり、内部の配線にダメージが蓄積している可能性も。
特に5年以上使用している場合は、コードの状態を確認し、必要であれば新しい製品に買い替えるのが安全です。
- コードが熱を持つ
- 焦げ跡や変色がある
- プラグ部分がぐらつく
これらはすべて“買い替えのサイン”です。
PSEマークがあるか、見た目に異常がないかもチェックポイント。見た目が少し古くなってきた、というだけでも注意して損はありません。
万が一のトラッキング火災や感電事故を防ぐためにも、早めに新しい製品へ買い替えるのが安心です。
せっかく新調するなら、USBポート付きや個別スイッチ付きなど、今のライフスタイルに合った便利なモデルを選んで、デスク周りをアップデートしてみましょう。
電源タップの選び方|失敗しないためのポイント

差込口の数と間隔をチェックしよう
延長コードの「差込口の数」は多ければ安心…と思いがちですが、使い方次第では“多すぎても邪魔”になることも。逆に少なすぎると機器を増やしたときに足りなくなりがちです。
特に注意したいのが「差込口の間隔」。ACアダプターや大きめの充電器を使う場合、差込口が多数に見えても、隣の口と干渉して使えないこともあります。
差込口の間が広めに設計されているモデルや、回転するタイプなどがおすすめです。
コードの長さは使い方に合わせて選ぶ
コードの長さも意外と重要なポイント。短すぎると延長の意味がなく、長すぎると足元で邪魔になることも。
目安は以下の通りです:
- 1m:机のすぐそばで使う場合
- 2m:少し離れた壁際から電源を取る場合
- 3m:部屋の反対側まで引っ張る必要がある場合
また、「巻き取り式」のコードなら使わない時にスッキリ収納でき、持ち運びにも便利です。
スイッチやUSBポートの有無も大切
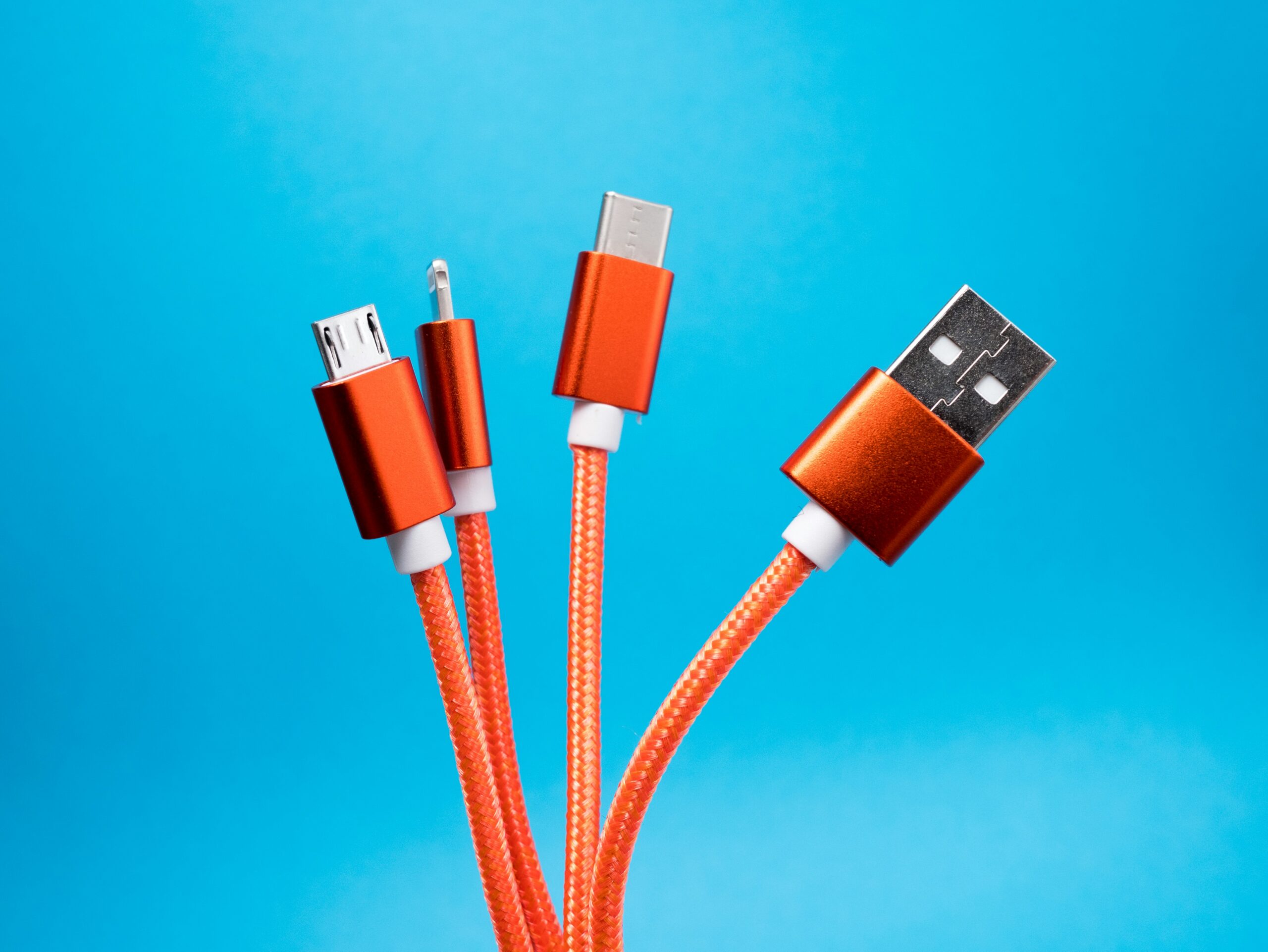
電源タップには「個別スイッチ付き」「全体スイッチのみ」などさまざまなタイプがあります。
・個別スイッチ: 使わない機器の電源だけをオフにできて省エネ
・全体スイッチ: 一括でオンオフができ、節電や消し忘れ防止に
さらに、USBポート(特にUSB Type-C対応)があると、スマホやタブレットの充電に直接使えて便利。差込口を消費せずに済むのも魅力です。
安全性は絶対に妥協しない
延長コードは電気を扱う機器である以上、安全性は何よりも重要です。
以下の機能があるかを必ずチェックしましょう:
- PSEマーク(電気用品安全法)取得済み
- 雷サージガード機能:落雷による過電流から家電を守る
- トラッキング火災防止プラグ:ホコリによる発火リスクを軽減
このうち最も重要なのがPSEマークです。
PSEマークとは「電気用品安全法」に基づいて、製品が国の安全基準を満たしていることを示すマークです。日本国内で販売される電気製品には、このマークの表示が義務付けられており、延長コードや電源タップも例外ではありません。
見た目や価格だけで選ばず、安全性能をしっかり確認して選ぶことが大切です。
設置場所に合う形状を選ぶ
電源タップには、設置スタイルに応じてさまざまな形状があります。
- 床置きタイプ: 最も一般的。家具の隙間や足元に。
- 壁掛け対応タイプ: 収納棚やデスク下に固定できてスッキリ。
- タワー型タイプ: 縦に差せるので省スペースで大容量。複数の機器をまとめて接続したい人に。
例えば、リビングのテレビ裏ならスリムな横長タイプ、デスク上なら壁掛け式やUSBポート付きなど、使うシーンをイメージして選ぶと失敗がありません。
3ピンプラグ対応の延長コードとは?

一般的な延長コードは「2ピン(平行の2本足)」のプラグに対応していますが、精密機器や高性能家電の中には「3ピン(2本の平行足+アース付き)」プラグを採用しているものもあります。
3ピン対応の延長コードとは、そのアース端子付きプラグをそのまま差し込める延長ケーブルのこと。主に以下のような特徴があります:
- 精密機器を安全に使える:PC・プリンター・プロジェクター・業務用機器など、アース付き機器で静電気や漏電リスクを軽減。
- 差し込み口に穴が3つ:2ピンプラグも3ピンプラグもどちらも使える構造になっています(製品によっては2ピン専用もあるため注意)。
- アース端子があるタイプもあり:壁のアース端子とつなぐことで、より安全性を高めることが可能です。
もし在宅ワーク用の高性能デバイスを安全に運用したいと考えているなら、「3ピン対応」と記載のある延長コードを選ぶと安心です。特に精密機器が多い作業環境では、ぜひチェックしておきましょう。
安全性・使いやすさで選ぶ|おすすめ電源タップ10選
USB付き・Type-C対応モデル|スマホなどの充電に
カシムラ NAC-042
特徴:USB-AとUSB-Cポートを1口ずつ搭載。合計最大出力3.4Aで、スマホ・タブレットの同時充電も可能。1mコード付きのコンパクト設計。
こんな人におすすめ:デスク周りでスマホやiPadの充電も一緒に済ませたい方に最適。
個別スイッチ付き|節電タップで待機電力を減らそう
KIMOC 電源タップ 6口 1m
特徴:6口すべてに個別スイッチ付き。雷ガードとほこり防止シャッターで安全性も◎。
こんな人におすすめ:使用機器ごとに電源をオンオフ管理したい方、節電を意識している方に。
スマートホーム連携可能|スケジュール・タイマー設定も
TOP-FLEX スマートプラグ
特徴:Wi-Fi対応でAlexaやGoogle Homeと連携可能。アプリでスケジュール管理や遠隔操作ができるスマート電源タップ。
こんな人におすすめ:スマートホーム化を進めたい方、自宅の家電を自動化・音声操作したい方に。
雷サージ保護付き|万が一の時に大切な電子機器を守る
エルパ (ELPA) サージ付タップ A-350SB(W)
特徴:雷サージ吸収素子内蔵で突然の雷による機器の故障を防止。コンパクトな3口設計で家庭内で使いやすい。
こんな人におすすめ:パソコンや家電を雷から守りたい方、安全性を重視する方に。
タワー式|省スペースで複数デバイスを同時充電できる
TOPREK 電源タップ タワー式 3m
特徴:縦型構造で省スペース。AC12口+USB5ポート(Type-C対応)を搭載し、計17デバイスを同時接続可能。
こんな人におすすめ:ガジェットが多い方やオフィス・会議室などで多用途に使いたい方に。
回転プラグ式|テレビ裏など狭い隙間でも設置しやすい
エレコム 電源タップ 回転機能タップ T-KF04-21010BK
特徴:プラグが180度回転可能。狭いスペースでも配線しやすく、雷サージ機能付き。
こんな人におすすめ:テレビ裏や家具の隙間など、設置場所に制限がある環境におすすめ。
抜け止め防止機能つき|プラグが誤って抜けるのを防止
エレコム 電源タップ マグネット付 T-ECOH3410NM
特徴:抜け止めコンセント搭載で不意な抜け落ちを防止。マグネット付きで金属面に固定可能。
こんな人におすすめ:足元や動線に近い場所で電源タップを使っている方、安全性を高めたい方に。
3ピンプラグ対応|OA機器などもアダプタなしで接続可能
エレコム 電源タップ 3ピン 7個口 T-T05-3720LG/RS
特徴:3ピン対応で、OA機器や高出力の電化製品に対応。雷ガード機能も備えた実用モデル。
こんな人におすすめ:業務用機器や3ピン専用機器を使用する在宅ワーカーやオフィス利用者に。
差し込みフリー|どこにでも挿せるからサイズに困らない
YAZAWA 差し込みフリータップ
特徴:差し込み場所が自由な構造で、大きなACアダプター同士でも干渉せずに接続可能。
こんな人におすすめ:複数のACアダプターを使う人、形状が異なる機器をよく使う人に。
クランプ付き|デスク・机などに仮固定ができる
サンワサプライ 電源タップ クランプ固定式 TAP-B53W
特徴:机の端に固定できるクランプ式。配線の整理がしやすく、集中スイッチ付きで管理も簡単。
こんな人におすすめ:作業机の上をすっきり整理したい方、電源の抜き差しをよく行う方に。
電気の基礎知識|コンセント・電源タップの定格容量とは
電源タップを安全に使い続けるには、「定格容量」や「消費電力」の知識が不可欠です。
特にパソコンやヒーターなど、電力を多く使う機器を扱う人は、トラブル防止のためにもぜひ押さえておきましょう。
電気の単位|アンペア・ボルト・ワットとは
電気に関する3つの基本単位は以下の通りです。
- アンペア(A):電流の量。水道で言えば「水の量」。
- ボルト(V):電圧。電気を押し出す力。水道なら「水圧」。
- ワット(W):消費電力。A(電流)× V(電圧)で求められます。
たとえば、日本の家庭用電源は「100V」が基本なので、15Aの回路なら
100V × 15A = 1,500Wまでが安全に使える上限ということになります。
家庭用コンセント・電源タップの基本は上限1500W
市販されているほとんどの電源タップや延長コードは「定格容量1,500W」と表示されています。これは「同時に使う電化製品の合計消費電力が1,500Wを超えないように」という意味です。
たとえば、パソコンやディスプレイ、加湿器、ヒーターなどを一か所にまとめてつないでしまうと、意外とすぐにこの上限を超えてしまう可能性があります。
同じ電源タップに繋ぎすぎると「過電流」に
1つの電源タップに複数の家電を同時接続すると、「たこ足配線」と呼ばれる状態になります。
この状態で1,500Wを超えて使用し続けると、「過電流」によってブレーカーが落ちたり、コードが熱を持って発火するリスクも。
特に冬場の暖房機器、夏場の冷却機器など、消費電力が大きい家電を同時に使うときは要注意です。
主な家電製品の消費電力目安
以下は、家庭やテレワークでよく使われる機器の、おおよその消費電力です。
|
家電・ガジェット |
消費電力の目安 |
|---|---|
|
ノートパソコン |
約50〜100W |
|
デスクトップPC |
約150〜300W |
|
液晶ディスプレイ(24型) |
約30〜60W |
|
スマホ充電器 |
約10〜15W |
|
デスクライト(LED) |
約5〜15W |
|
電気ストーブ |
約1,000W〜1,200W |
|
電気ポット |
約700〜1,000W |
|
加湿器 |
約200〜500W |
このように、複数の家電を同時に使う場合は合計ワット数をしっかり確認し、タップの「定格1500W」を超えないように注意しましょう。
延長コード・電源タップの設置で失敗しやすいポイントと対策
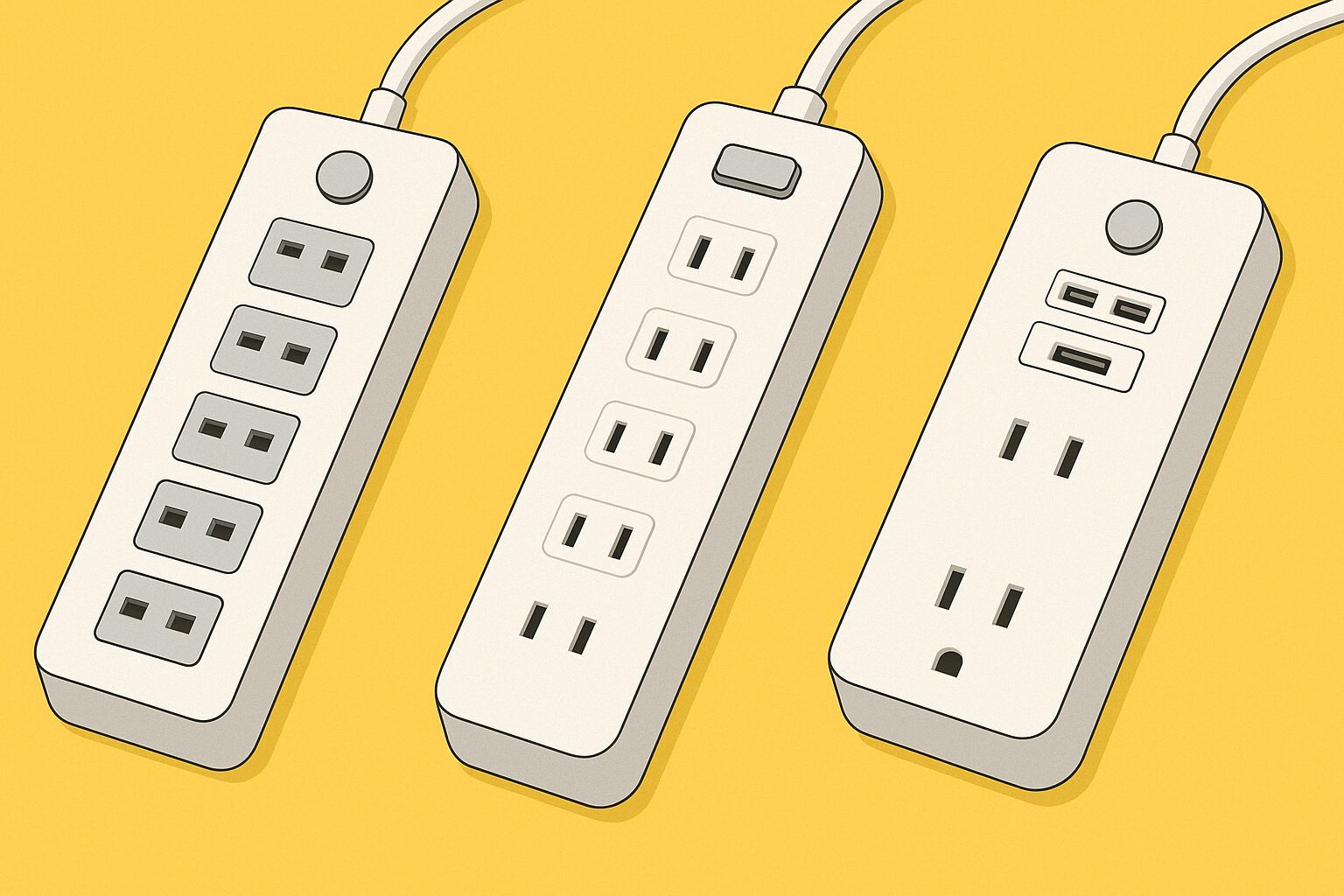
差し込み口が足りない・間隔が狭い
意外と多いのが「口数が足りない」「ACアダプター同士が干渉して使えない」という失敗。
延長コードを購入するときは、使用予定の機器数より「1〜2口多め」にするのがベター。
また、ACアダプターの幅が広い場合は「間隔が広め」「差し込みフリー構造」のタップを選ぶとストレスなく使えます。
コードが長すぎて邪魔になる
「長めが便利そう」と思って3mコードを買ったら、足元で絡まって邪魔に…というパターンも少なくありません。
コードの長さは、使用場所までの距離+少し余裕がある程度が理想です。必要以上に長いと、巻きぐせや絡まりの原因に。
整理しやすい「巻き取り式」「コードクリップ付き」などのモデルを選ぶのも有効です。
タップが見えて見た目が悪い
せっかくおしゃれなデスクを整えても、電源タップが丸見えだと一気に生活感が出てしまいます。さらにホコリや足元の接触でトラブルの原因になることも。
そんな時は「ケーブルボックス」や「配線カバー」を使って、タップごと隠してしまうのがスマート。
床置きタイプなら、デスク下に収められるボックスタイプが人気。壁際設置なら、目立ちにくいカラーや縦型のタップもおすすめです。
Q&A|延長コード・電源タップのよくある疑問
Q. 延長コードの寿命ってあるの?
はい、延長コードにも寿命があります。目安としては【約5年】が推奨交換時期とされており、これをすぎると被膜の劣化や内部断線のリスクが高まります。
以下のような症状がある場合はすぐに買い替えましょう。
- コードが固くなっている
- プラグに熱を持つ・焦げ跡がある
- 使用中に接続が不安定になる
「使えるから大丈夫」は危険。安全のために定期的な点検・更新を!
Q. USB付きタップはスマホ充電に悪影響?
基本的には問題ありません。PSE認証がある信頼できる製品であれば、USB充電ポートからスマホ・タブレットの充電を安全に行えます。
ただし、以下の点に注意しましょう:
- 安価すぎるノーブランド品は避ける
- 電流出力(例:2.4Aなど)を確認し、スマホに合った出力のものを選ぶ
- 同時に複数台充電すると出力が分散され、充電が遅くなることがある
Q. 電源タップにドライヤーや電子レンジは使える?
基本的にはNGです。
なぜなら、ドライヤーや電子レンジは消費電力が1000W〜1400Wと高く、延長コードを介して使用すると過電流のリスクがあるからです。
特に他の機器と同時に使う「タコ足配線状態」では、定格容量(1500W)を超える可能性大。ブレーカーが落ちたり、火災につながることもあるため、直接コンセントへ接続するようにしましょう。
Q. タコ足配線は本当に危険?
タコ足配線そのものがすぐに危険というわけではありませんが、使い方次第で非常に危険になることがあります。
以下に当てはまると要注意です:
- 定格容量(1500W)を超える機器を同時に使っている
- 電源タップの上にほこりがたまっている
- タップ同士を重ねてつないでいる(二重タップ)
火災原因にもなりうるため、配線の整理と安全な使い方を意識しましょう。
まとめ&関連記事
「配線が整うと、気持ちも整う」
延長コードや電源タップは“裏方”の存在ですが、だからこそ見落としがちな安全リスクを秘めています。火災の予防はもちろん、在宅ワークの快適さを底上げするためにも、使い方と選び方をしっかり見直すことが重要です。
- 「とりあえず家にあるもの」で済ませていた人ほど、変えてみると驚くほど快適になるはず。
- 「正しい延長コード選び」は、日々の安心と効率アップ、そして災害予防にもつながります。
安全で快適な作業環境づくりの第一歩として、この記事を参考にご自身の配線環境をぜひ見直してみてください。
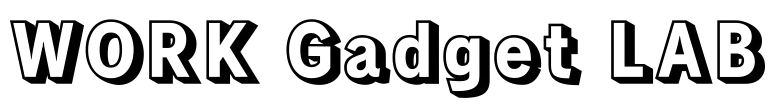
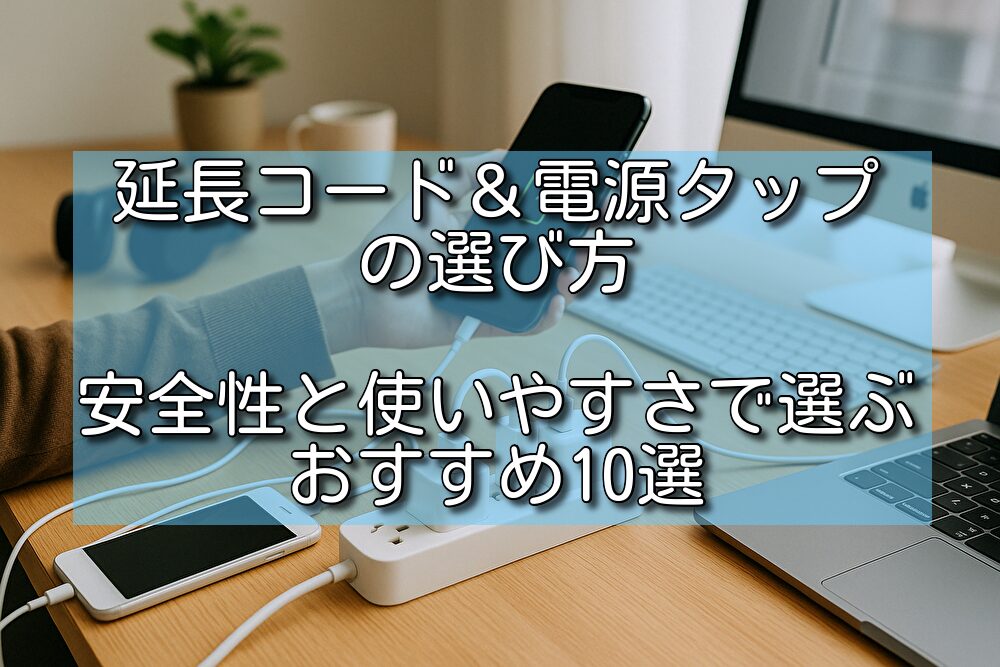
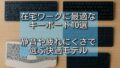
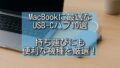
コメント